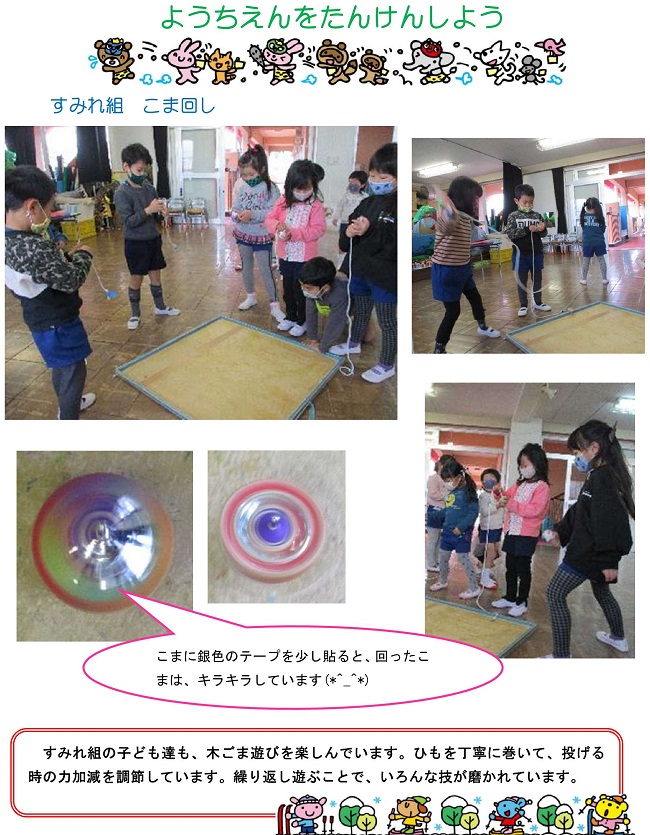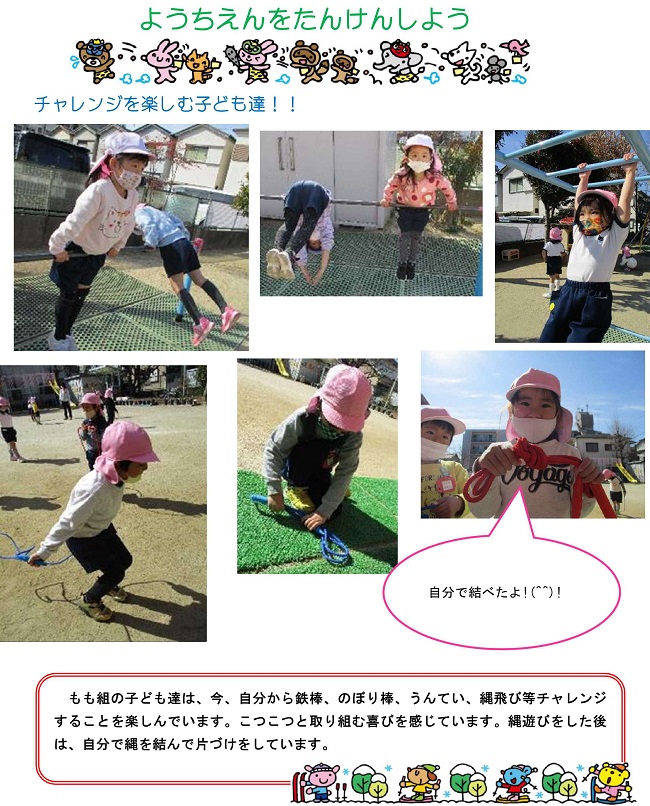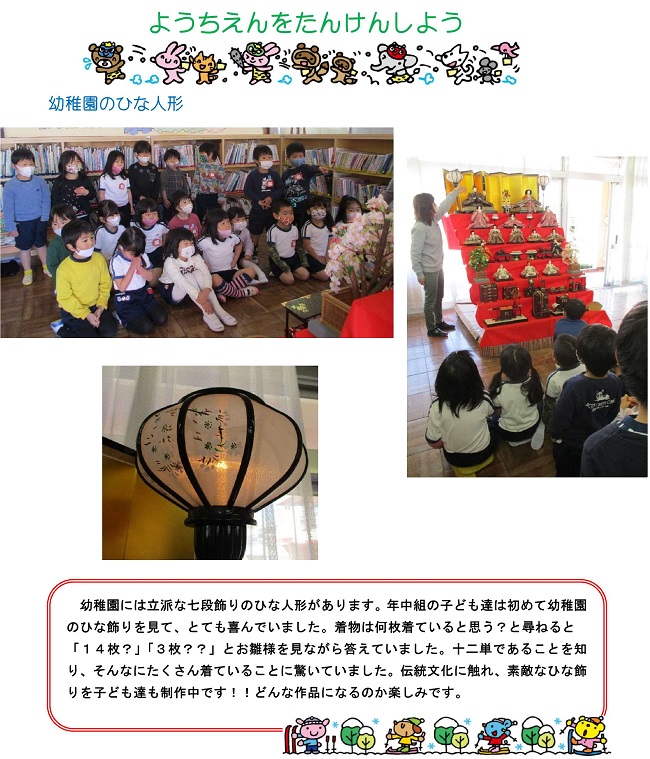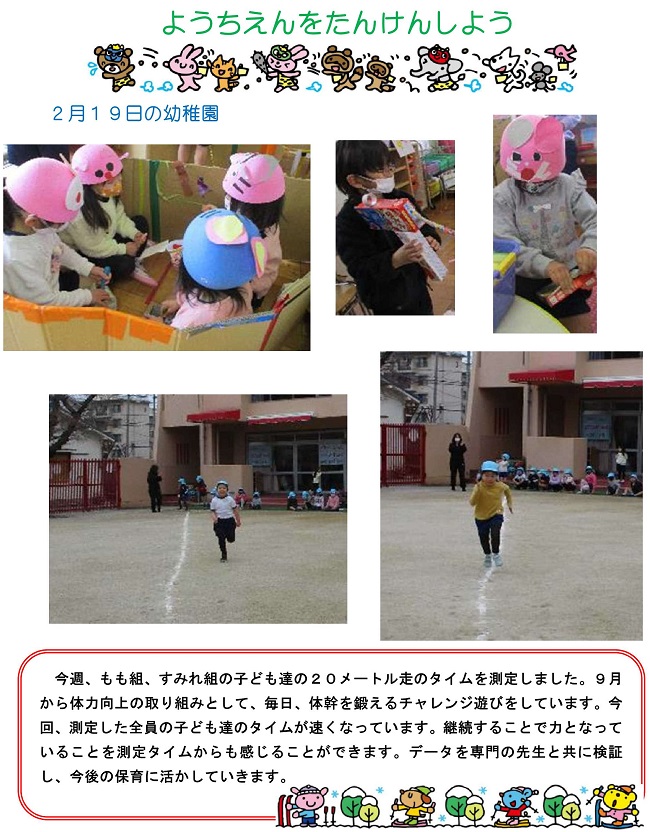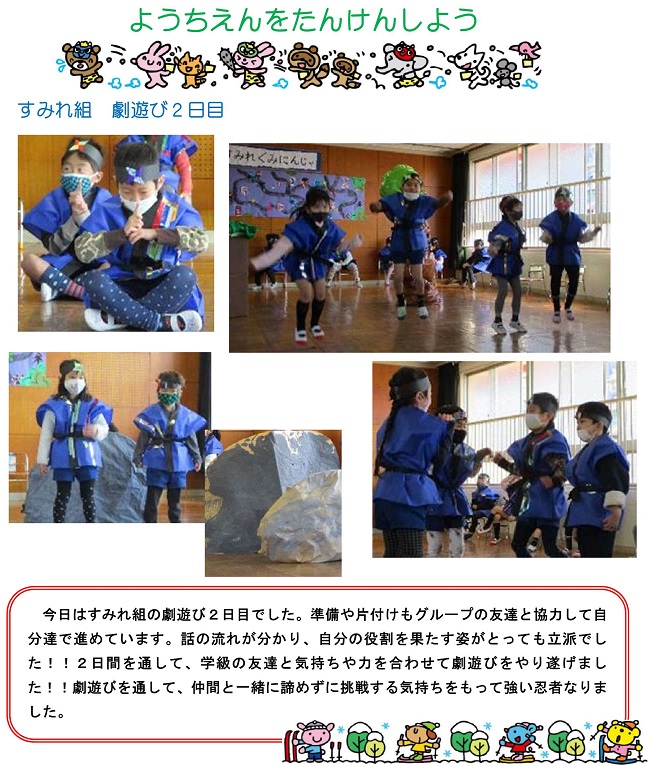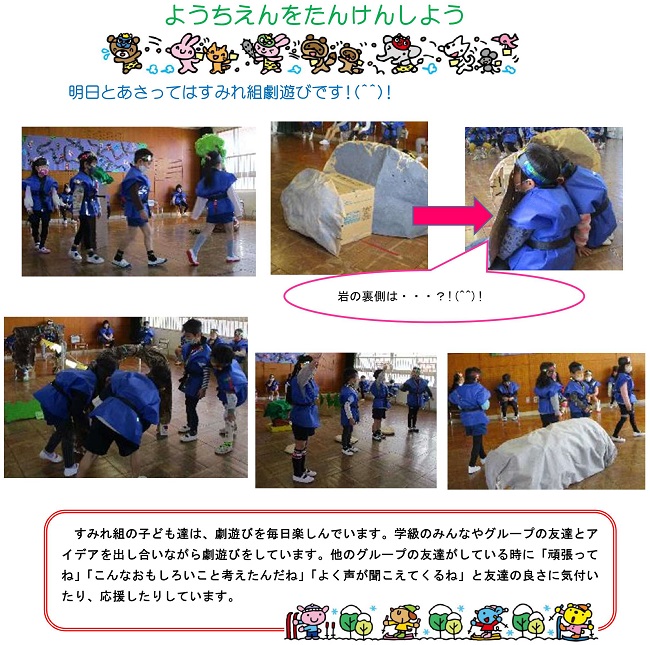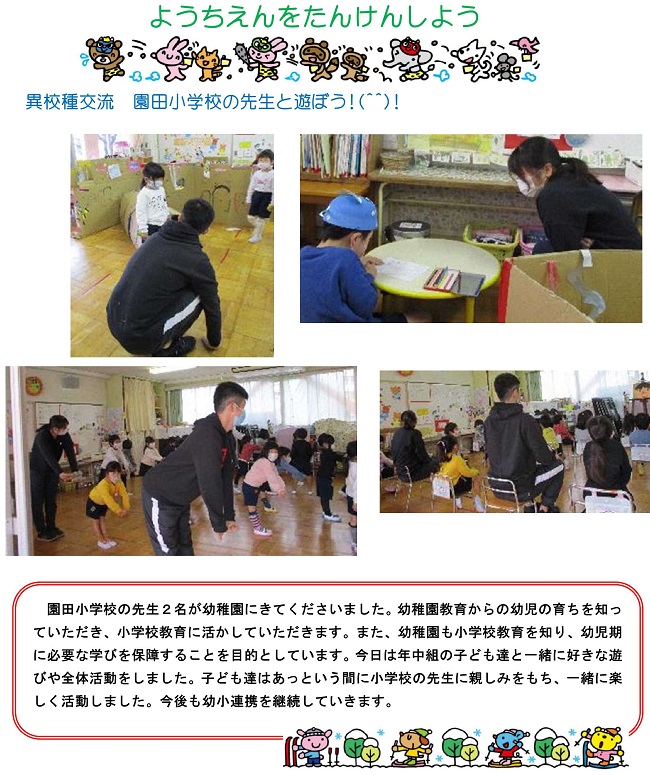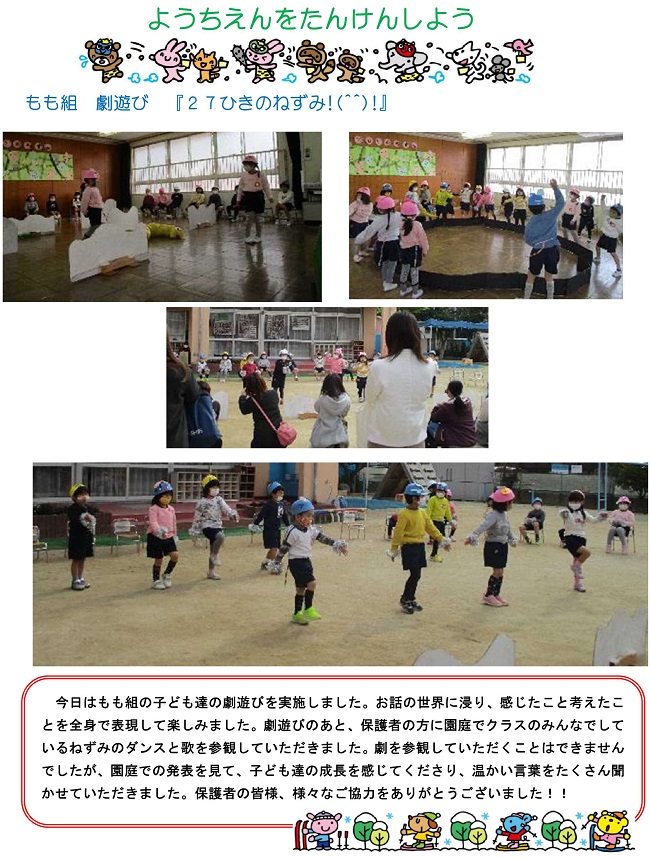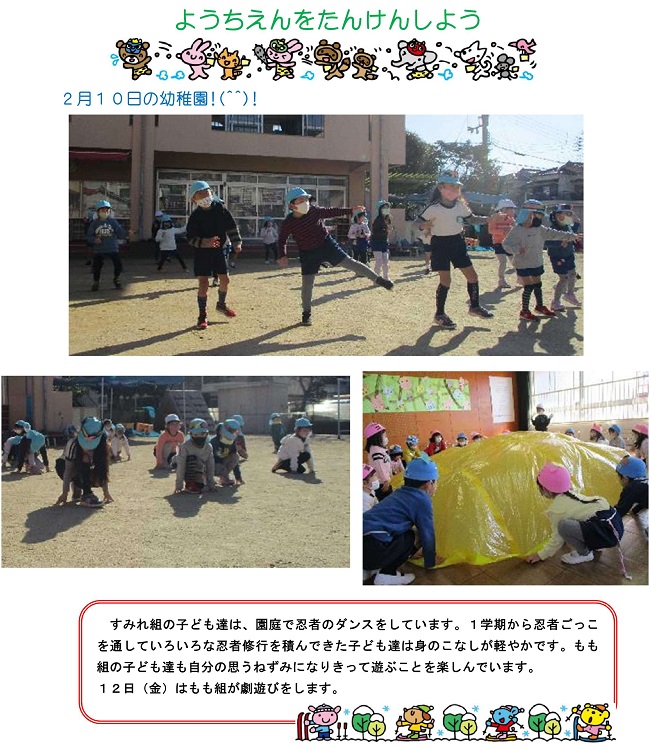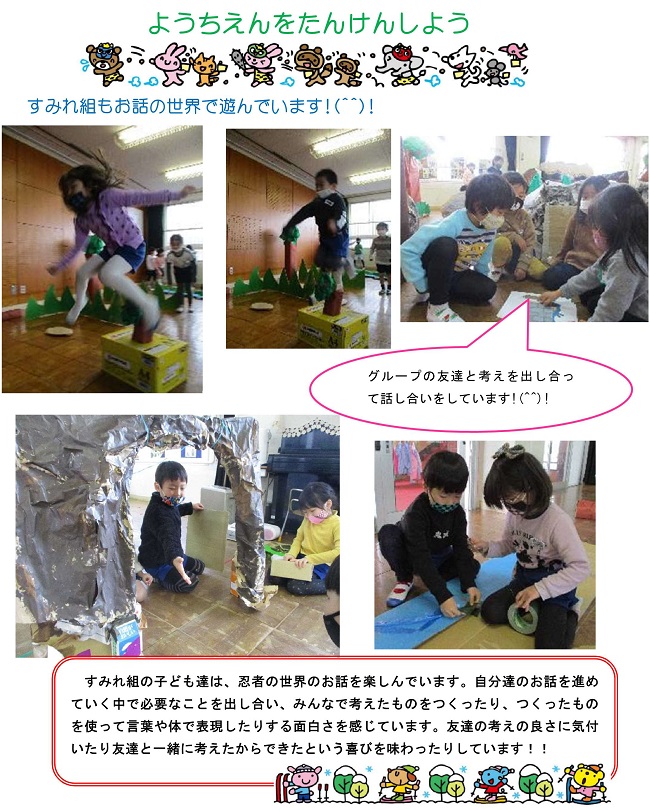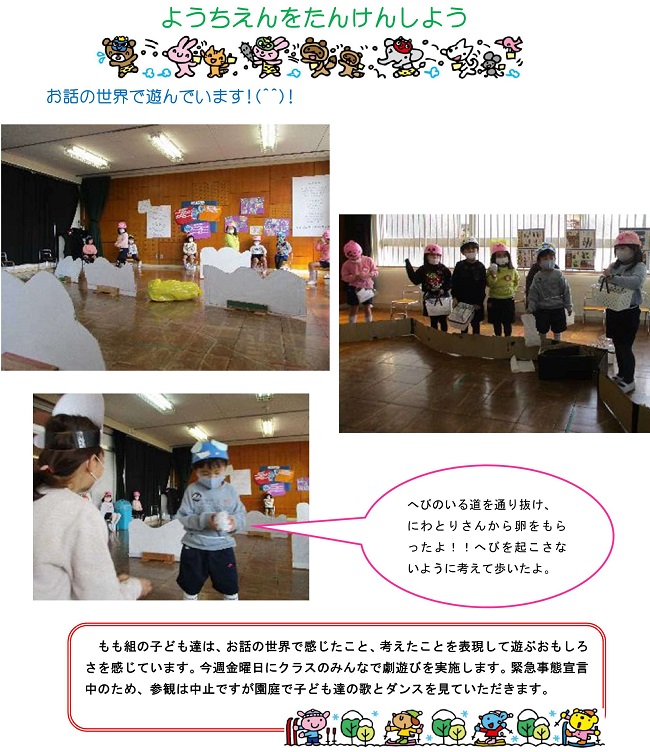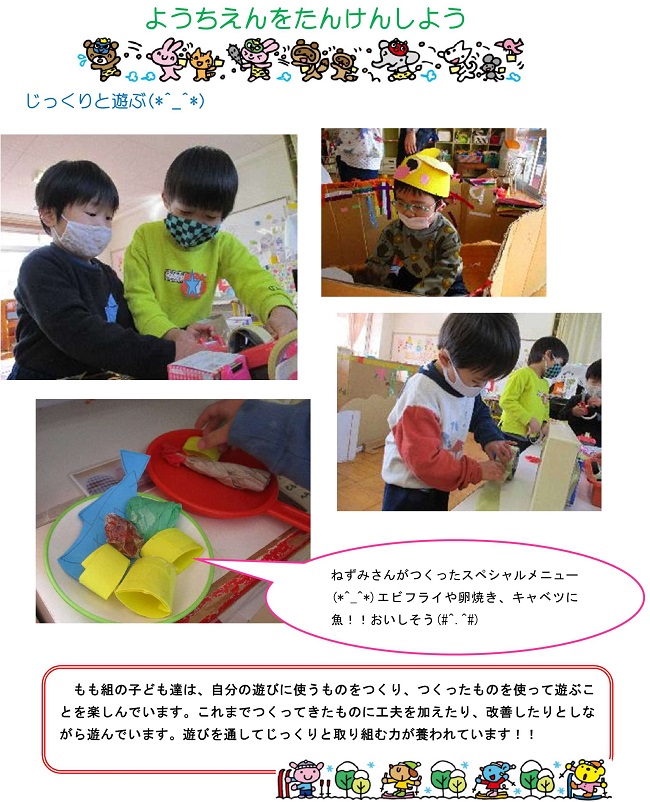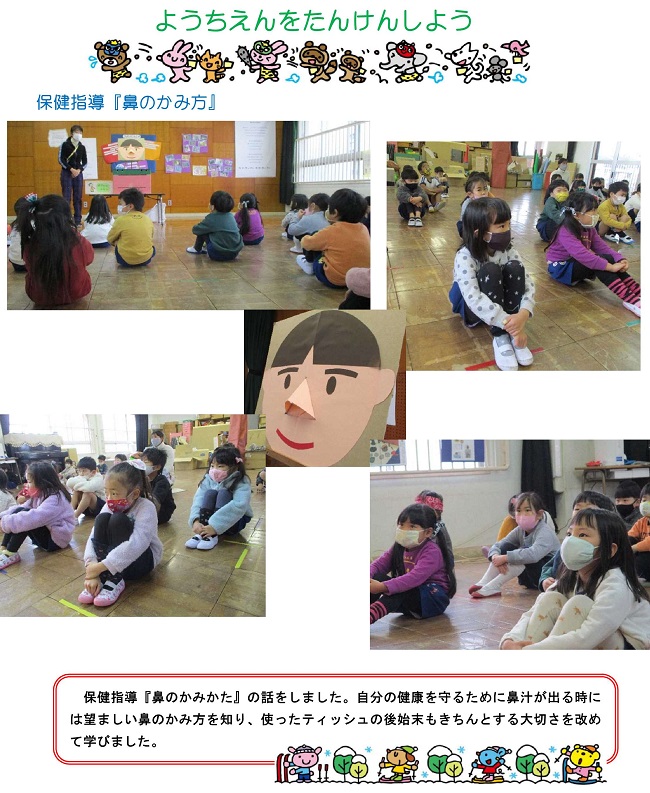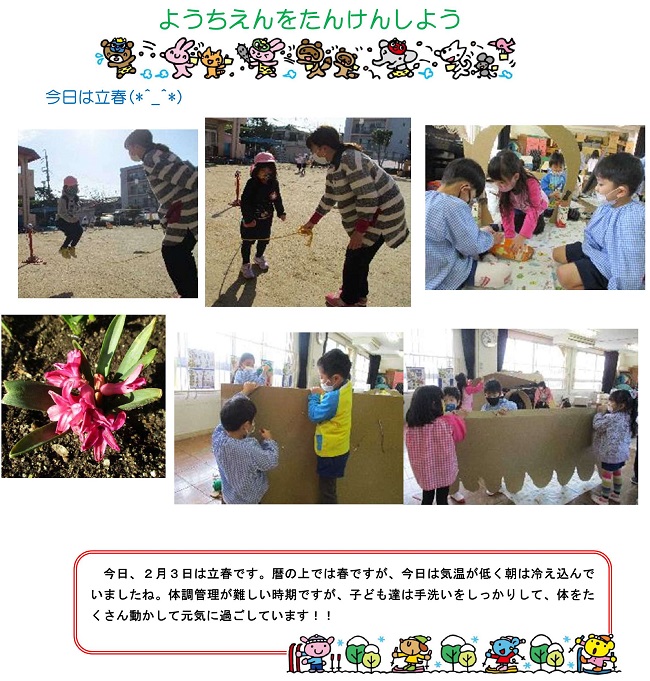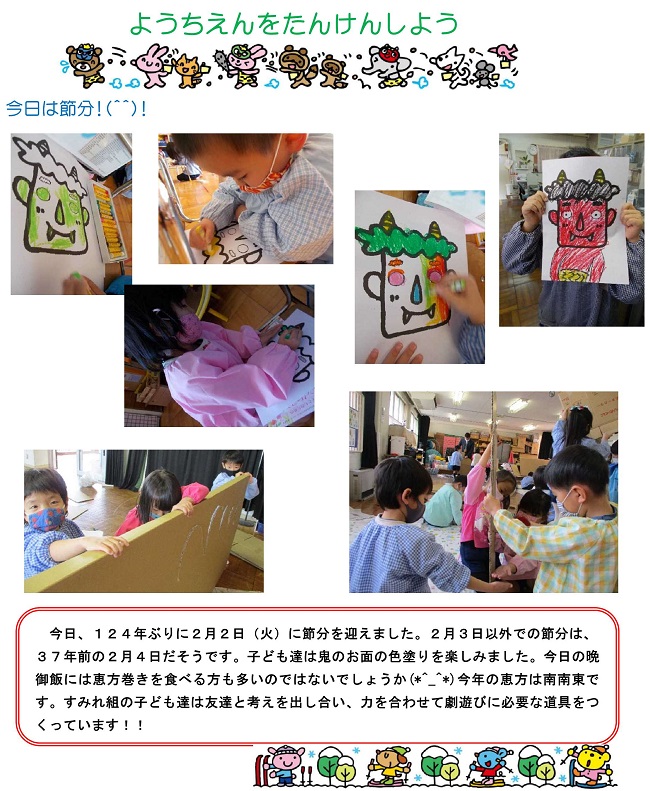「感じる」読み聞かせ
毎月、お誕生会を行っています。
月ごとの子ども達のお誕生日をクラスみんなでお祝いします。お家でも当然お祝いしてもらっていますが、クラスみんなでお祝いの歌を歌い、「おめでとう!」の言葉を贈ります。
一人一人にそれぞれの写真と手形、メッセージが入った記念のバースデーファイルと写真付きのキーフォルダーがプレゼントで贈られます。
もらった子ども達は、反応がそれぞれ違います。はにかむ子、「ありがとう」とはっきり言う子、ファイルの中を一生懸命見る子、どの子も家に帰ってから家族でもう一度一緒に見ながらお話をすることでしょう。そこには普段以上に心に感じるものがあり、生まれた時の話が出たり、幼稚園での話が出たり、赤ちゃんの時、高い熱が出て心配したこと、初めて立った時のことを思い出したり…次から次へと育ちのエピソードが数珠つなぎで思い出されることでしょう。
感じると言えば、お誕生日会で園長先生からのプレゼントのコーナーがあり、毎回年長組、年中組に別の絵本の読み聞かせをしています。
絵を見せながら絵本を読むのは難しいです。まず、子ども達を引き付ける内容の本を選ぶ。絵本を見ながら、子ども達の反応を見てお話が良く伝わる読み方をする。
分かりにくい、興味の持てない内容、長すぎてもだめ、伝わりにくい読み方もだめ、幼い、語彙も少ない子ども達によく分かり、ドラマがあり、何かを感じる、そう、この何かを感じることが大切。そんな読み聞かせがしたいのです。
何かを感じる読み聞かせに近づけると、はっきり態度やコメントが帰ってきます。私の場合、ほとんどが「長いお話―。」「しーん。」など、反省する反応がほとんどです。
大人の私たちは頭が先行しがちで、あれこれ考えすぎて子どものように素直に感じることが弱くなっている気がします。
素直に感じる。このことを見つめ直せば、子ども達の感じる心に近づき寄り添えるのかも…。(腹黒さが渦を巻く私の心も澄んだ青空のように…)
読み聞かせが「感じる」を育てるよう努力します。

 ハッスル!ハッスル!~園長ブログ Vol.52(2/26)
ハッスル!ハッスル!~園長ブログ Vol.52(2/26)