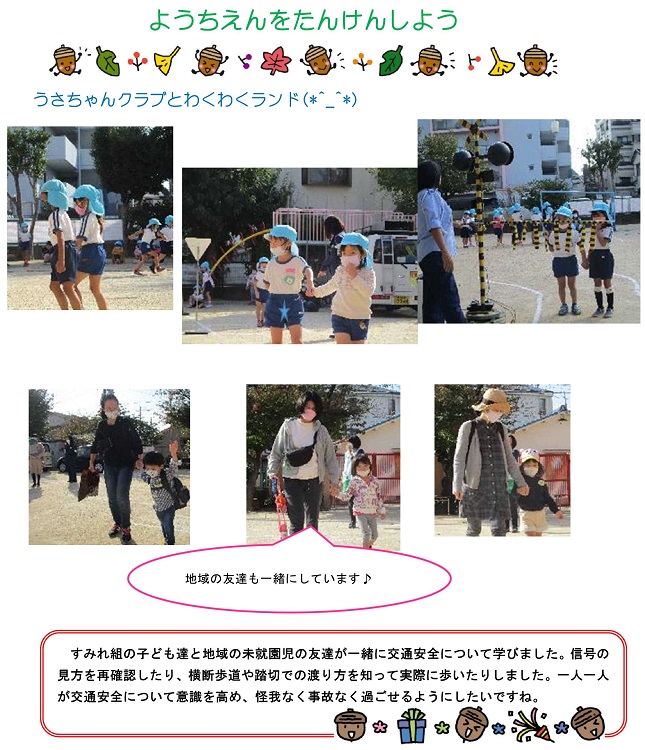
小園中学校キャリア教育講師で参加
今、小園中学校2年生キャリア教育の講師を終えて帰ってきました。
今年はトライやるウィークがない為、上記の行事が計画され、園田地域課を通じて講師を依頼されました。講師は、地域の尼信、郵便局をはじめ全部で17の事業所の方々が参加しました。1回25分を3回しました。小園幼稚園の園長先生と交代で行い、3回目は導入を小園幼稚園の園長先生にやっていただき、あとを話させていただく即興コラボですすめました。
さすが、歌と動作で生徒たちをのせる小園幼稚園の園長先生、私も勉強になりました。
生徒たちは聞く態度が良く、大事だと思うことはメモをしっかり書いているようでした。
将来のことを考えている生徒が何人かいるようで、目的に向けて準備に取り掛かっている生徒がいました。他の人はまだだと言い、それが普通で、「それでいいのだ。」とパワーポイントのスライドを出しました。生徒たちの人生は先が長いです。「色々なことに首を突っ込んでみるうちに何か見つかるよ。」と話しました。私もその様な感じでした。今に至るのは友達や先生とのいい出会いがあったからです。だから、「その時その時のことを一生懸命取り組もう。それを大事にしてほしい。」と伝えました。
私が幼稚園の園長になるまでの簡単な紹介から園田幼稚園の保育や幼児教育で大事にしていることを話しました。あれもこれも話したいことが次々浮かび、質問の時間がないグループもあり、申し訳なかったです。
最後のところで、少し大げさですが、「生きる力」を身に付けて欲しい願いから、「とにかく勉強しよう。自ら学べる力をつけよう。」と伝えました。お説教がましいことですが、私は親に感謝していることがこのことなのです。働き詰めの両親が読書環境だけは整えてくれました。このことが、目の前の課題を自分で調べ、解決方法を考えようとする姿勢につながったのだと思います。(大抵は人に助けられて何とかなったというところですが)
あと2校でお話の機会をいただいています。児童生徒の応援団として「ハッスル!ハッスル!」と声援をおくってきます。
遊びからひろがる育ち
今日も快晴。
太鼓のトントントントン…、連打が2階から聞こえて来ると、ドドドドドドドドド、大勢が走り回る響きが階下の職員室に響いてきました。何をしているのかなと2階へ上がり、年長すみれ組さんの様子を見に行きました。
遊戯室の壁沿いにみんな座り、あるグループの子ども達が忍者走りの低い姿勢をとって、障害物を飛び越え、走り、飛び越え、走り…と、ぐるぐる回り続けていました。合図で止まり、次の修行は飛び越えるのに両足ジャンプです。走って、足グーでジャンプ、その繰り返しでぐるぐる走ります。腰と右足が痛んでいる私も、子ども達の頑張る姿につられ、途中から割り込みました。やってみると大変。低い姿勢で走るだけでも大変。間隔がまちまちの障害を飛び越えたり、両足ジャンプで飛び越えたり、運動に変化があります。動作をうまく調整しなければなりません。一つのグループが終わったら次のグループといきいきと取り組みました。
ちょっとやってへとへとの私は、こっそり忍者走りで年中もも組さんの部屋へ逃げ込みました。
年中さんは、先日から地域の方からいただいたどんぐりや職員が里山から集めてきたどんぐりをころがして遊んできました。坂道を色々作り、一つずつ転がしたり、一度にたくさんバラバラと転がしたりして、様々な方向に転がる様子を見て、キャッキャッと飛び上がって喜んでいました。今月のうたも「どんぐりころころ…♪」を歌っています。
今日は、そのつながりで、絵の具を使ってどんぐりの絵を描いていました。大きなダイナミックな絵もあれば、小さなどんぐりが画面いっぱいに描かれている作品もあります。遊びを通じてどんぐりへの思いは子ども達それぞれです。
遊びから子ども達の育ちにつながる活動が広がっています。
カラフル園田幼稚園
今日は抜けるような青空、快晴です。
登園した子どもたちは、手を消毒したあと各々自分のじょうろを取りに行きます。たらいに汲んでいる水にじょうろを入れて水をくみ取り、自分の植木鉢のところへ向かいます。大きく元気に育つよう願いながら水やりをしているのでしょうか。
終わったらじょうろを元に戻し、園舎で迎える先生のところ駆け寄る子、ゆっくり歩み寄る子様々です。先生たちは明るく「おはよう、〇〇ちゃん、今日も元気だね。いい笑顔だね。」と迎えています。
年中もも組さんは、クロッカスとチューリップを先週植えました。年長すみれ組さんは、色とりどりのパンジーを植えました。そのだっ子はお花を大切に育てています。
園庭が華やぐのが楽しみです。
園田幼稚園勉強中 その2
先ほど研究会が終わりました。
その1の続きを思い出しています。雨が降っていたので予定していたサッカーごっこは中止でした。あとは、忍者ごっことどんぐり滑り台をすみれ組とゆり組の部屋で行いました。
忍者ごっこで手裏剣修行の壁を作っている子は段ボールカッターで窓の様なものをくり抜いて作っていました。様々な窓の形を工夫していました。仲間と協力して窓の縁取りも作っていました。
どんぐり滑り台は、パチンコ台かスマートボール台(昭和前期の人しか知らないかも)のような台やながーいコースの台、垂直にペットボトルの筒をどんぐりが通っていく台など、グループごとに相談して工夫をして、どんぐりの実をころがして試し、楽しんで作っていました。ダイナミックなのは大きな段ボールで作った忍者屋敷です。迷路のような通路を通って部屋から部屋へ移動できるのです。また、大きな屋根を付け、内張に黒いビニールを貼り、光が外から入らないよう工夫していました。忍者なのでこっそり外から見えないように工夫しているのかも知れません。私では到底通れない細い通路を子ども達は器用にすり抜けていました。仲間と作って試して、さらに改良、工夫をしてより良いものに仕上げていく。
そのだっ子は体験を通じ、人と関わりを持ち成長していっています。
私達教職員も、勉強中。子ども達のためにより良い保育ができるよう頑張っています。
さようならピアノ
おだやかな秋の朝。我が家のピアノが旅立ちました。(10月24日)
20年余りの長い間、音楽好きの家族を支え、楽しみの友としてリビングで過ごしました。阪神淡路大震災もともに生き延びました。我が子の育ちに寄り添い、見守ってきたピアノ。
リビングから小さな庭に運ばれ、クレーンに吊り下げられ、トラックの荷台へ。
次は、どこかの家へ運ばれ、音楽好きな家族のもとへ行くことでしょう。その家の小さな子が小さな指でたどたどしいながらも、キラキラした音色を奏でることでしょう。あるいは、どこかの幼稚園で活躍してくれるかも。
別れの淋しさを感じましたが、どこかで子どもたちの心を育んでくれることでしょう。
園田幼稚園勉強中 その1
本日は雨。
園庭は水浸し。足元が悪い中を親子で登園いただいています。来るだけで大変なことです。今朝、ある女の子が、私と話している中で「雨の日、お母さんたいへんやねん。いつもおくってくれて。」と言いました。子どもはよく分かっているんですね。改めて言ったりはしませんが、心でしっかり感じとっています。
さて、本日は園内研究の日です。二人の先生方に保育の様子を見ていただき、ご指導いただきました。私たちの指導力向上のため、講師の先生に何度かご指導をいただいています。
まず、年中さん。どーなつやさん、ザリガニごっこ、箱などで好きなものをつくる制作。自由に思い思いの遊びを楽しました。
どーなつやさんは、紙で作ったどーなつを屋台風のお店に並べ、さらに、カップケーキのような色とりどりのお菓子も並べ始めました。店員さんやお客さんになり切ってやりとりしています。もも組の部屋の真ん中に段ボールの家をつくり、真ん中のテーブルに色とりどりのお菓子をきれいに並べ、まわりに5脚の椅子を置きました。和やかに交流する姿は、幸せな時間が流れていました。
ザリガニごっこは、上手に大きな紙を切って作ったザリガニのツメを手に付け、かえるちゃんのお面をかぶって追いかけたり、かくれたりして、成り切って遊びました。
さらに、箱の創作は、剣や銃、魔法のバトン、あと?な、おもちゃ?…とにかく喜んで思い思いのポーズをとってあそんでいました。
紙面?が尽きましたので、ひとまずページを閉じます。年長さんは次回に続く。
※前回、誤って年少を年小と表記いたしました。年少の誤りです。ここにお詫びと訂正いたします。またあるかも知れません。(温かい目で知らないふりをお願いします。または、こっそりそっと教えてください。)
いいわけは、いいわけないが…
まず、最初にお詫びと訂正をいたします。
先日までの文章に、年中組と書くところを年小組と書いているところがあります。わが子が幼稚園の時、年小、年長と言っていたので、今も頭で変換しながら言っています。それがうっかり出てしまったようです。もし、またありましたら心の中で(年小?年中のつもりで書いてるんだ。これをとがめだてすると、顔は鬼瓦だけど、ガラスのハートの園長先生だし…まっ、気付くだろうからそっと見守ってあげよう)と思い、ご容赦願います。
さて、昨日は父の病院での検査、診察、治療で1日介護のお休みをいただきました。となりは、小児、乳幼児の診療科があり、生まれたばかりのお子さんや就学前、小学生ぐらいのお子さんなどが、前の通路を通ります。看護士さんや病院スタッフの方々と保護者がお子さんのことで真剣に話す姿、笑顔で話す姿が見られます。受付からでしょうか、呼び出す声が時々聞こえ、温かく包むような声音で呼びかけています。さりげない些細なことかもしれませんが、不安な気持ちの患者さんや家族にどれだけ支えとなることか。
保育者である私たちも、さりげなく、温かくそのだっ子に声がけができるよう努めていきたいと思いました。
リレー大好き
そのだっ子はリレー大好き。
お昼から年少さんは自由遊びを園庭でしました。お天気もよくポカポカ陽気となりました。そこで、10名ほどの子ども達で年長さんが運動会でやっていたリレーをしようということになりました。コースは少し短く小さいトラックにしまし。チームはどのように分けたか分かりませんが、自発的に帽子をピンクと白に組分けしているではありませんか。スタート位置もきちんと決め、よーい、ドン!
何周か競走しているうちに、突然とび入りした子がリングバトンを受け取り走り出しました。1周回ってきて次の子にバトンパス。あれ?そのまま2週目へ。さすがに疲れたのか次の子へバトンパス。本人はそのまま他の遊びへ去っていきました。割り込みに誰一人怒ることもなく、そのままリレーは続きました。途中で転ぶ子もありますが、すぐ立ち上がり次の人へバトンをパスしようと一生懸命走ります。友達とひたすらバトンを渡し、思い切り走り、次へバトンを渡す。大人では勝ち負けのルールを決めていますが、子ども達はまだルールを決めていません。ただ、バトンパスをする、思い切り走るリレーをしたい。それだけで始めたリレーです。何回も力を抜くことなく今を一生懸命走るリレーでした。
子どもは今をただ遊びきる。うーん禅に通じるなあ、何て、すぐ頭で小難しく考えようとしてしまう大人の私。
でも、何か大事なことを子ども達に教えてもらった気がします。
とったど―‼
サツマイモを掘りました。
園庭の2か所の花壇でうねをつくりサツマイモを育てていました。このうねは、ボランティアで来ていただいている地域の先生につくっていただきました。
年長さんは2チームに分かれ、ながーーーいイモのツルを引っ張ってとりました。ツルにはサツマイモがいくつかくっついてとれました。「わー、イモだー!」と歓声があがりました。土の中からもっとサツマイモが出てくるかも。年長さんの期待は高まります。うねごとに分かれ、素手で土を掘り掘り、「あっ、イモだ!」「引っ張ったらダメだよ、周りの土をとるんだよ。」と声をかけ合いながら、指をくま手のようにして土をガリガリ、ガリガリ。イモをにぎり、プチッ。「とったどー!」とったイモを空に向かって高らかに差し上げました。
「わー!」驚きと喜びの混じった歓声が上がりました。よーし、僕も、私も見つけようとさらにガリガリ、ガリガリ。「あった!」「見つけた!」「ほんとだ!」と大きなイモ、かわいいイモ、色々なイモが掘り出されました。
みんなで記念の写真を撮り、とったツルでも綱引きの様ことをしたり、なわとびをしたり、体に巻き付けて何かに変身したりして、思い思いのことを友達と考えて楽しみました。
さわやかな秋空のもと、楽しいサツマイモ掘りができました。
突然の第二運動会!?
運動会の翌日(10月14日)。年長組さんが運動会でした『ソーラン』の音楽が園庭に流れ、園庭を見に職員室を出ました。何と、年中組さんが『ソーラン』を踊りだしたのです。そこに二階から年長組さんが降りてきて、応援するように、また、お手本を見せようと一緒に参加しだしました。園庭がそのだっ子全員の『ソーラン』で大爆発。「ヤーレン、ソーラン!ヤーレン、ソーラン!」の声も本番を超えそうなくらい園庭に響き渡りました。
その後、年中組さんの「カエルのみどりちゃん♪~」と曲が流れると、年中組、年長組のダンスが園庭いっぱいに広がり、カーニバル状態。感心なことにその中でもソーシャルディスタンスを子ども達が自然に意識できている。練習、本番とそのだっ子は一生懸命取り組み、お互いの演技をよく見ていたことがよくわかりました。
そして、何よりうんどうかいの演技を子ども達が心から楽しみ、やり遂げた満足感と自信を持ってくれたことの証であると思いました。
職員も思わず喜びの歓声と手拍子、飛び入り参加してしまいました。(だから、ビデオ撮影できていません(; ;))
本番も素敵でしたが、今日は年中組さん、年長組さんが自ら節度を持ち、いきいきとし、一つになれた姿に感動しました。
保護者のみなさんに見ていただきたかったです。ほんとに…一緒に感動を分かち合いたかったです。
(職員だけ子ども達と素敵な体験をさせていただきました。ありがとうございました。)
園長 多 田 弘